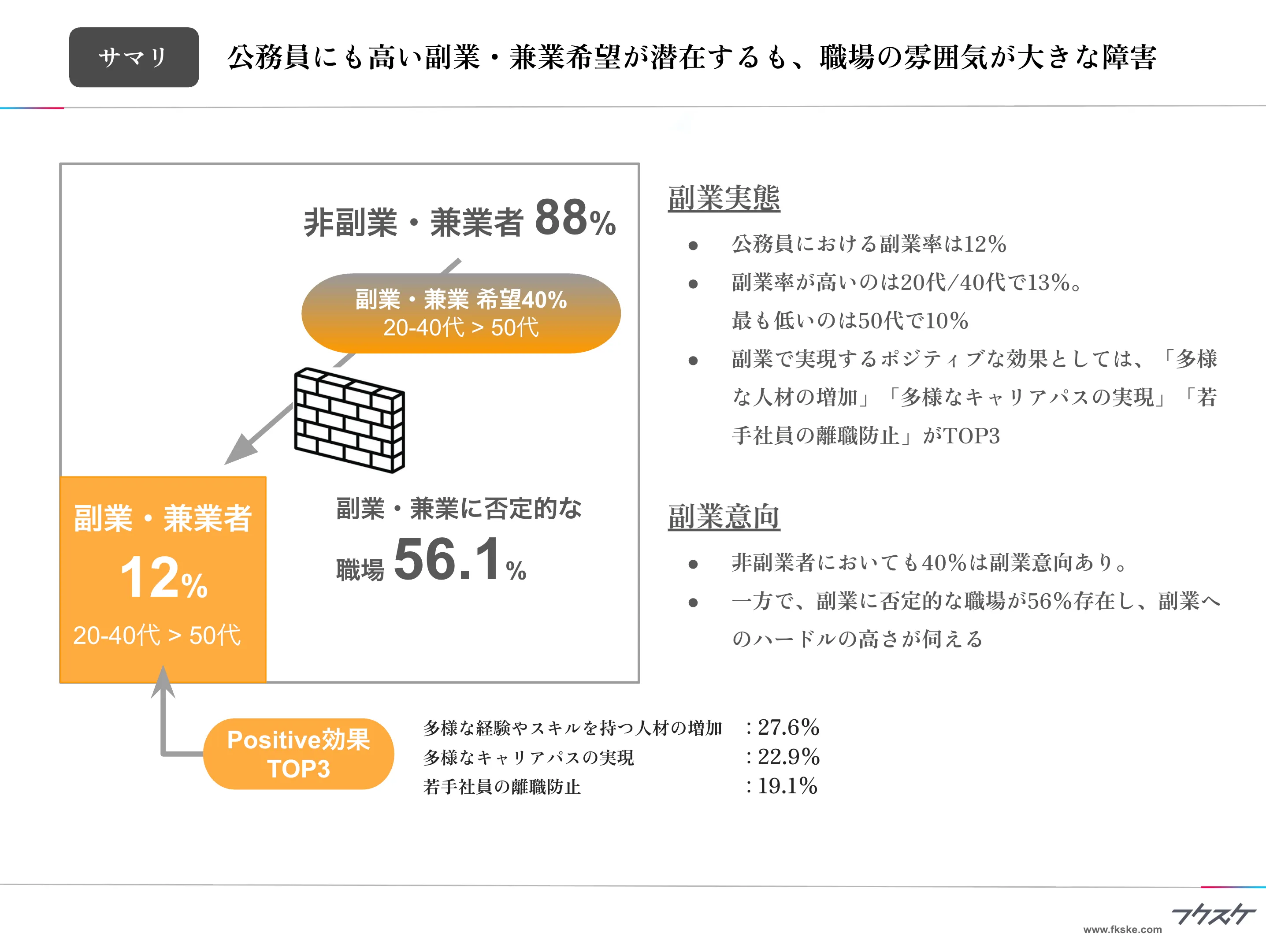副業が在職中の競業化になる場合は?不正競争防止法の営業秘密とは【前編】

(1)従業員等による営業秘密の不正利用の問題

従業員や役員(以下「従業員等」という。)の副業を認める場合の大きな懸念の一つは、従業員等による、副業先での自社の営業秘密の漏えいや不正利用であろう。
前提として、労働契約の信義則上の付随義務として、在職中、営業上の秘密情報(以下「営業秘密」という。)を秘密として保持する義務(秘密保持義務)を負うと解されている。また、従業員だけではなく、会社役員も会社法上の忠実義務(会社法355条、民法644条)に基づき、同様の秘密保持義務を負う。
したがって、少なくとも在職中の秘密保持義務については、従業員等が雇用又は委任契約上当然に負うべき義務であり、従業員等が在職中に副業する場合、この秘密保持義務に違反しない範囲で行わなければならず、雇用契約書や就業規則に明文の記載がないからといって、営業秘密を利用して良いということにはならない(もっとも、多くの企業は、従業員等に対し、入社時に秘密保持誓約書、雇用(委任)契約書、又は就業規則により秘密保持義務を課していると思われる。)。
(2)営業秘密を秘密として管理することの重要性
では、副業を行う役員等による営業秘密の漏えいを防ぐためにはどうすれば良いか。
厚労省の副業・兼業ガイドライン(以下「副業ガイドライン」という。)では、「就業規則等において、業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと」「 副業・兼業を行う労働者に対して、業務上の秘密となる情報の範囲や、業務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること」等が考えられると述べられている。実務上は、後者の点が不十分となるケース、つまり、雇用契約書や就業規則において従業員等に対して秘密保持義務を課しておきながら、従業員等に対して営業秘密に該当する情報であることを示していなかったとして、営業秘密該当性が否定されるケースが散見される。
すなわち、不正競争防止法上の営業秘密(法2条6項)が定義する「営業秘密」(これを「狭義の営業秘密」と呼ぶこともある。)に該当するためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)、及び③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を全て満たす必要があるが、実務上、営業秘密の要件が否定されるのは、①の秘密管理性を欠くケースである。

一般に、秘密管理性とは、営業秘密を保有する者の秘密管理意思が、秘密管理措置によって、従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があると解されており、具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員等の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるが、企業における営業秘密の管理単位における従業員等がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要があるとされている(近時の裁判例として、東京地裁令和4年12月26日労政時報4056号12頁・伊藤忠商事ほか事件)。
つまり、実際上、従業員等がある情報について秘密情報であると現実に認識していれば、厳密なアクセス制限までは必要はないと考えられるものの、何らの秘密管理措置がなされていない場合には、秘密管理性要件は満たされない傾向にある。要するに、企業としては、従業員等による「秘密だとは思わなかった」「誰でもアクセスできた」といった言い逃れを防ぐことができる程度に、秘密管理性を担保するための措置を講じておく必要があるといえよう。
実務上の方策としては、例えば、①重要な情報については営業秘密であることを明示する、②営業秘密へのアクセス権者の設定範囲を改めて確認し、当該営業秘密にアクセスする必要のない従業員がアクセスできないようにする、③社内教育の実施や社内規程の周知等を通じて、秘密情報管理の重要性に関する従業員の理解を深め漏えいに対する危機意識を高める、④情報漏えい行為を実施しにくい状況を作り出すための工夫(メールの送信・転送制限、遠隔操作により社用PC内のデータを消去できるツールの利用、社用PCにUSBメモリやスマートフォン等を接続できないようにする等)が考えられる。

(3)不正競争防止法上の営業秘密に該当することの意味
なお、仮にある情報が不正競争防止法上の営業秘密に該当しなくとも、その情報の不正利用や漏えいが契約上の秘密保持義務違反に該当する場合はあるが、営業秘密が不正競争防止法上「営業秘密」に該当し、その不正利用や漏えい等が不正競争行為となる場合、その行為者は営業秘密侵害罪に問われ刑事罰が科されることになり、民事上も、同法に基づき営業秘密の利用の差止め、廃棄等を求めることができ、損害額も法律上の推定が働くという強力な効果が生じるため、不正競争防止法上の営業秘密に該当するかどうかは、営業秘密の問題を考える上で重要な問題となる。
(4)従業員等による漏えいや不正利用の立証の問題
また、別の問題として、従業員等が営業秘密を漏えいしたり不正利用したりしている事実を立証することが難しいという問題もある。つまり、従業員等が「不正な手段」により営業秘密を持ち出し、また不正に利用している事実を、どのように検知・把握するかという問題である。

まず、不正な持ち出しについては、例えば、事前の方策として、従業員等による営業秘密へのアクセスやダウンロードについて、PCやスマートフォンのログを保存したり、事後の方策として、データの暗号化による閲覧制限、パスワード認証に一定回数失敗した場合に秘密情報を消去できるツールの利用等により営業秘密の流出先を把握したり、流出先等による営業秘密へのアクセスを制限するといった方策が考えられる。
他方、従業員等による営業秘密の使用の立証については、従業員等の私用PCの調査を、強制力をもって行うことは困難であるし、営業秘密侵害罪について刑事処罰を求め、その刑事手続における捜査関係資料を証拠とすることも考えられるが、時間的・コスト的制約が重くのしかかる。
そのため、現状は、当該営業秘密を使用していることについて、間接事実(例えば、営業秘密である製造方法を利用しなければ通常製造が不可能な製品を製造している、営業秘密である顧客名簿に載っている顧客の多数に(新たに)営業をかけている等の事実)から、使用の事実を立証していくことが基本となろう。
もっとも、オープンイノベーション・雇用の流動化を踏まえた令和5年の不正競争防止法改正(令和6年4月に施行予定)による「使用等の推定」の拡大により、これまで非常に限定的であった使用の推定規定の適用対象が拡大され、①営業秘密に対してもともとアクセス権限を有していた者(元従業員)が、営業秘密が記録された媒体等を許可なく複製等(領得)した場合や、②不正な経緯を知らずに転得したが警告書等によりその経緯を事後的に知った者が、記録媒体等を削除等しなかった場合にまで及ぶことになった。
推定規定が適用されると、逆に被告側が、独自の生産方法で生産等しているなど、営業秘密を使用していないことについて立証しなければならなくなるから、営業秘密侵害を主張する当事者の立証ハードルを大きく下げることになる。

(5)副業を行う従業員等を受け入れる企業のリスク
逆の立場として、副業を行う従業員等を受け入れる企業は、当該従業員等が、その所属先企業の営業秘密を不正に利用したりしてしまうと、使用者責任(民法715条1項)により、当該所属先企業に対して損害賠償責任を負うリスクがある。このようなリスクを回避するためには、採用前においても、①前勤務先における業務内容、②採用募集に応募した経緯、③前勤務先との間での秘密保持義務や競業避止義務の有無及び内容といった事項を確認し、所属先企業で使用している情報やデータは一切利用不可とした上で、採用後には、秘密保持義務等に関する誓約書を作成することが考えられる。
また、万一、営業秘密の不正利用を知った場合には、直ちに当該営業秘密を廃棄すべきである。不正利用を知ったにもかかわらず、営業秘密を廃棄しなければ、上記のとおり、改正不正競争防止法施行後は、「使用等の推定」が適用されてしまうことになるからである。
副業制度で「在職中の競業化」をコントロール、制度担当のための競業避止の基礎知識【後編】

執筆者
上田 雅大 森・濱田松本法律事務所カウンセル弁護士森・濱田松本法律事務所カウンセル弁護士。2009年神戸大学法学部卒業、2010年弁護士登録(63期)、2016~2018年厚生労働省労働基準局に出向、2019年コーネル大学ロースクール修了(LL.M.)後、2020年McDermott Will & Emery(Washingto...