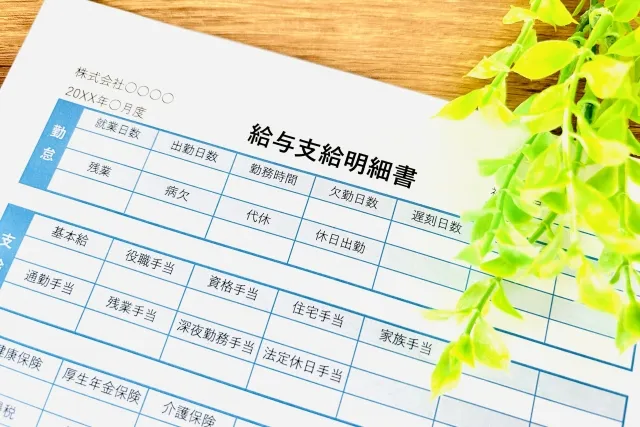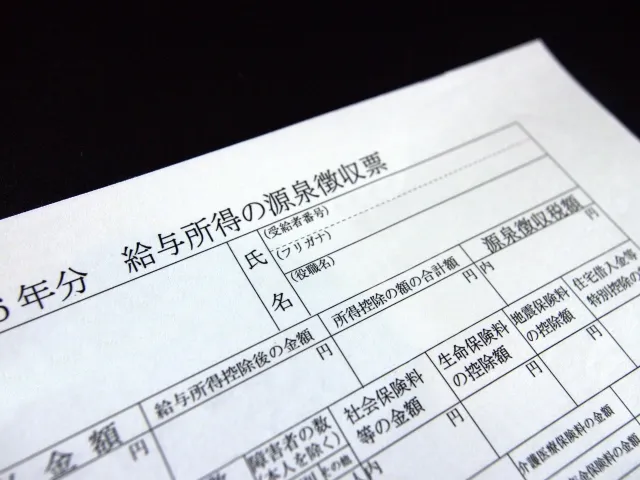社員の「投資」は副業扱いになる?人事が知っておくべき境界線と対応策
社員の「投資」はどこまでが許容範囲で、どこからが「副業」として扱われるべきか、人事担当者にとって判断が難しい問題です。
近年、資産形成への関心から社員が様々な投資を行うケースが増えていますが、その内容や規模によっては本業への影響も懸念されます。
この記事では、投資と副業の基本的な考え方から、副業と見なされる可能性のある投資ケース、そして人事担当者が取るべき具体的な対応策までを詳しく解説します。
投資は副業にあたるのか?基本的な考え方

社員の「投資」が「副業」にあたるのかどうかは、多くの人事担当者が一度は直面する疑問かもしれません。
ここでは、まず押さえておくべき基本的な考え方と、なぜ一般的な投資が副業と見なされにくいのか、その理由を掘り下げていきましょう。
原則として投資(株式・投資信託・NISAなど)は「副業」ではない
社員が行う株式投資や投資信託、NISAといった一般的な金融商品への投資は、原則として「副業」にはあたりません。
これらは主に個人の資産形成を目的とした「資産運用」と見なされるため、労働の対価として収入を得る副業とは性質が異なります。
例えば、NISAは資産運用の一環として利用される制度であり、副業禁止の会社でも安心して利用できるケースがほとんどです。株式投資も同様に副業とは見なされず、公務員でも行うことが許可されています。
労働を伴わず、資産運用とみなされるケースが大半
投資が副業と区別される主な理由は、その活動に「労働の提供」が伴わない点にあります。
一般的に、副業とは本業以外で自身の時間やスキルといった労働力を提供し、その対価として報酬を得る活動を指します。これに対し、株式投資や投資信託などの一般的な投資は、自己の資産を金融市場などに投じ、その運用成果として配当金や売買差益といった利益を得る行為です。
ここには、企業に雇用されて働くような明確な労務提供は発生しておらず、投資は副業には該当しないと解釈されるのです。
就業規則や厚労省の副業ガイドライン上でも、一般的な投資は副業に該当しないとされる
多くの企業の就業規則では副業が禁止または許可制とされていますが、株式投資や投資信託といった一般的な投資活動は、この副業規定に抵触しないと解釈されるのが一般的です。
これは、厚生労働省が示す「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の考え方にも沿っています。このガイドラインによれば、投資は労働の対価として報酬を得るものではないため、副業として扱われることは少ないとされています。
そのため、たとえ勤務先が副業を禁止していたとしても、通常の範囲で行う株式投資や投資信託などの資産運用は、問題ないとされるケースが大半です。
例外もあり?「副業」と見なされる投資ケースとは
多くの投資は副業に該当しないとされますが、全てのケースでそうとは限りません。
ここでは「副業」とみなされる可能性が高い投資を3つ紹介します。
人事担当者としては、これらの例外的なケースをしっかり把握し、従業員への適切な指導や、必要に応じた対応ができるようにしておくことも重要です。
不動産投資(5棟10室基準)の扱い
アパートやマンションなどの不動産投資は、その規模によって副業と判断される場合があります。目安としてよく用いられるのが「5棟10室基準」です。
これは独立家屋なら5棟以上、アパートなどであれば10室以上を所有・賃貸している状態を指し、これを超えると税務上「事業所得」と見なされ、企業からも副業扱いとなる可能性が高まります。
また、個人ではなく法人化して不動産投資を行っている場合も、事業性が高いと判断され、副業に該当すると見なされることが一般的です。
FXや仮想通貨のデイトレード
FXや仮想通貨の取引そのものは、多くの場合、資産運用の一環と見なされます。しかし、これらの取引の中でも、特に1日に何度も売買を繰り返す「デイトレード」のようなスタイルは注意が必要です。
勤務時間中に頻繁に取引を行ったり、取引に没頭するあまり本業に支障が出たりするようであれば、職務専念義務違反など就業規則に抵触する可能性があります。
FXや仮想通貨といった投資の種類よりも、本業への影響度により「副業」と判断され、罰則の対象になるケースがあるのです。
他者への出資・共同事業に近いケース
他者の事業への「出資」は、通常、資産運用の一環と見なされます。しかし、以下のように、関与の仕方によっては「共同事業」と評価され、副業に該当するケースがあります。
-
経営への積極的な関与
-
実態が業務委託や労働提供
このように、単なる資金提供に留まらず、自身の時間や労働力を提供し、事業運営に積極的に関与していると判断される場合は、副業と見なされる可能性が高まります。
投資と副業の線引きを人事としてどう捉えるべきか

社員の投資と副業の境界線は時に曖昧であり、人事担当者にとって判断が難しいケースもあります。企業としては社員の資産形成の自由を尊重しつつも、本業への支障や企業秩序の維持といった観点から一定のルールを設ける必要があるでしょう。
ここでは、その線引きをどのように考え、運用していくべきかを解説します。
判定のポイントは「労働の有無」「本業への影響」「継続性」
社員の投資活動が副業に該当するかを判断する際、人事担当者はいくつかの重要なポイントを総合的に見る必要があります。主な判断基準を以下にまとめました。
| 判断基準 | 詳細 |
|---|---|
| 労働の有無 | ・活動が労働力の提供か(副業該当) |
| 本業への影響 | ・勤務時間中の取引や活動の有無 |
| 継続性・事業性 | ・活動の頻度や期間 |
これらの要素を個別のケースごとに照らし合わせ、就業規則や副業ポリシーに基づき、企業として一貫性のある判断を下すことが重要です。
社員から申告を受けた場合の対応例
社員から投資活動に関する相談や申告があった際、人事担当者はまず丁寧なヒアリングを心がけましょう。確認すべき主な内容は以下の通りです。
-
投資の種類:株式・不動産・FX・出資など
-
活動の規模:投資金額・物件数・取引量など
-
費やす時間や頻度:週に何時間・1日に何回取引するかなど
-
具体的な活動内容:管理方法、経営への関与度合いなど
ヒアリングした内容を基に、自社の就業規則や副業ポリシーと照らし合わせ、副業に該当するかどうかを判断しましょう。
人事担当者がとるべき管理と制度設計

社員の投資活動が多様化し、副業への関心も高まる現代において、人事担当者には適切な管理体制と明確な社内制度の設計がこれまで以上に求められています。
無用なトラブルを未然に防ぎ、社員が安心して本業に集中しつつ、私生活での資産形成にも取り組めるような環境を整備することは、企業と従業員の双方にとってより良い関係構築に不可欠といえるでしょう。ここでは、そのための具体的な方策を解説します。
投資を就業規則にどう位置付けるか
社員の投資活動に関して公平な対応をするためには、就業規則でその位置づけを明確にすることが重要です。
そのためには、「副業に該当しない投資」と「該当する可能性がある投資」を明記することが有効的です。
| 副業に該当しない投資 | 副業に該当する可能性がある投資 |
|---|---|
| ・上場株式への投資 | ・事業的規模の不動産投資 |
何が許容され、何が許可を要するのかを社員が明確に示すことで、無許可での副業該当投資を防ぎ、企業として公平な対応をとることができるでしょう。
副業ポリシーと申告制度の整備
投資を含む副業全般について、企業としての方針を明確化した「副業ポリシー」を策定し、全社員に周知することが重要です。
副業ポリシーに盛り込むべき主な内容
-
本業への支障がないこと
-
情報漏洩リスクがないこと
-
企業ブランドを損なわないこと
-
競業避止義務や利益相反に該当しないこと
-
投資で申告が必要となる具体的なケース
このポリシーに基づき、副業をする際には事前に会社へ申告する「申告制度」を整備します。
申告制度の整備によって、企業は社員の副業状況を適切に管理しやすくなり、潜在的なリスクを早期に発見しやすくなります。また、社員にとっても、許容される活動範囲が明確になり、安心して副業や投資に取り組める環境が整います。
【まとめ】社員の投資と副業、人事は適切に判断しよう
社員の投資活動は、原則として「資産運用」であり副業には該当しません。しかし、一部の不動産投資やデイトレードなど、副業と見なされるケースも存在します。
企業の人事担当者としては、就業規則や副業ポリシーを明確に定め、申告制度を適切に運用することで、トラブルを未然に防ぎ、社員が安心して本業に取り組める環境を整備できます。
環境が整備されることで、社員は健全な資産形成を進められ、企業は秩序を維持しつつ従業員を支援することが可能になるでしょう。
運営