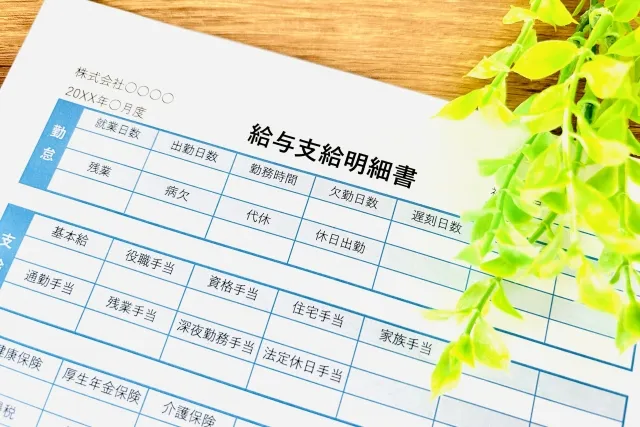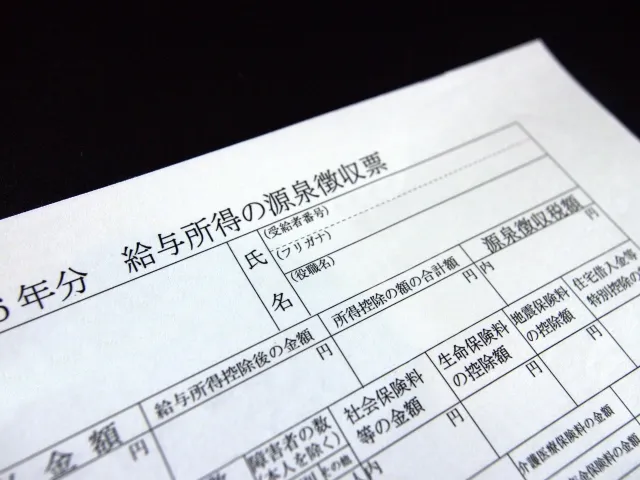社員がコーチングで副業していたら?トラブル事例や対処方法をご紹介
社員がコーチングの副業を行う際、収益化の自由度が高い一方で、トラブルに発展するリスクも存在します。
本記事では、コーチングが副業に該当する条件や、企業が取るべき対処法、実際のトラブル事例について詳しく解説します。
リスクを最小限に抑え、適切に副業を運用するためのポイントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
社員がコーチングをしていたら「副業」にあたる?

社員がコーチング活動を行っている場合、それは「副業」に該当するのでしょうか?結論としては、収益を目的としてコーチングを継続的に行っている場合、副業とみなされる可能性が高いです。
副業とは、本業以外に収入を得るための活動全般を指します。会社員として働きながら、たとえコーチングが趣味の延長線上であったとしても、クライアントから報酬を得ている場合は副業にあたります。
社員がコーチングの副業をしているときの対処法
ここからは、社員が副業をしている場合の対処法として、職業規則で副業を「禁止している場合」と「禁止していない場合」それぞれの対処方法を解説します。
就業規則で「副業」を禁止・制限している場合
企業が就業規則で副業を禁止または制限している場合でも、社員のコーチング副業を即座に禁止できるわけではありません。社員の勤務時間外の活動は、原則として個人の自由であり、会社が無条件に制限することは難しいからです。
しかし、以下のような特定のケースでは、例外的に制限や禁止が認められます。
-
労務提供上の支障がある場合
-
企業秘密が漏えいする場合
-
会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
-
競業により会社の利益を害する場合
上記のいずれかに該当する場合、就業規則に基づき、コーチング活動の内容を精査した上で、禁止または制限を検討する必要があります。
就業規則で「副業」を禁止・制限していない場合
就業規則で副業を許可している場合でも、企業の利益や業務遂行に悪影響を及ぼさないよう、一定のルールを設けることが重要です。社員がコーチング副業を行うことを会社に届け出た場合、以下の点を確認し、必要に応じて就業規則の改定や個別の契約を検討しましょう。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 労務提供への影響 | コーチングの副業が本業の業務遂行に支障をきたさないかを確認する |
| 企業秘密の管理 | ・自社の機密情報を利用しないようにする |
| コンプライアンスの遵守 | ・著作権・肖像権・名誉毀損などの法令遵守 |
| 競業避止 | ・会社の事業と競合する形で副業を行うことを禁止する |
副業を認めている場合でも、会社の利益を損なう可能性がある場合は、活動内容の変更、または活動の停止を求めることができることを明確に伝える必要があります。
社員のコーチングによるトラブル例
ここでは、社員のコーチング副業で起きたトラブルを3つ紹介します。
-
不当な支払い形態で活動している
-
しつこい勧誘活動を行っている
-
利用した人がマインドコントロール被害に遭っている
思わぬトラブルを避けるためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。
不当な支払い形態で活動している
近年、社員のコーチング副業に関する支払いトラブルが増加しています。
特に、法外な料金を請求する詐欺的手法や、コーチングを入口にしたマルチ商法や宗教勧誘へと発展するケースが多発しており、企業側も社員の活動に注意を払う必要があります。
コーチングには決まった料金体系がなく、業界全体での標準的な価格設定も存在しません。そのため、クライアントが相場を把握できず、不当に高額な料金を支払ってしまうケースがあります。
また、コーチングを装った手口として、以下のような危険なビジネスモデルが問題視されています。
-
コーチングをきっかけに、マルチ商法や危険な宗教団体への勧誘を行う
-
無料または低価格の初回セッションで集客し、段階的に高額な支払いを求める
社員のコーチング副業が、不当な支払い形態や悪質な勧誘の温床になってしまうリスクを企業は十分に認識する必要があります。
しつこい勧誘活動を行っている
コーチング業界においては、過度なしつこい勧誘が問題視されています。本来、コーチングはクライアントの自主的な成長を促すものですが、中には無理な契約を迫ったり、強引に知人を紹介させたりする悪質なケースも存在します。
こうした行為が広まったことで、「コーチング=怪しい」といったイメージを持たれる原因にもなっています。以下のような手法を用いるコーチは注意が必要です。
-
執拗に有料コースを勧める
-
断っても何度も連絡をしてくる
-
知人の紹介を強要する
しつこい勧誘活動は、クライアントとの信頼関係を損ない、社員個人や企業の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。企業は社員のコーチング活動を適切に管理し、トラブルを未然に防ぐことが重要といえるでしょう。
利用した人がマインドコントロール被害に遭っている
コーチングを悪用した洗脳・マインドコントロール被害も発生しています。悪質なコーチによるマインドコントロールは、初めは普通のコーチングと見分けがつかないことが特徴です。
多くの受講者は、「人生をより良くする」「ビジネスの成功につながる」と信じてセッションを受け始めます。しかし、次第に以下のような危険な手法が使われるようになります。
-
人格否定や恥をかかせる行動を強要する
-
恐怖心を植え付ける
-
依存関係を作る
このようなマインドコントロールが行われた結果、高額な費用を請求されたり、コーチングとは無関係な商材を買わされるなどの被害が発生しています。
社員がコーチング副業を行う際に、このような悪質な手法を用いることは、企業の信用を大きく損なう可能性があるので、事前に倫理規定やガイドラインをしっかりと設けておきましょう。
社員がコーチングの副業でトラブルを引き起こしてしまったら?
社員がコーチングの副業でトラブルを起こした場合、企業は状況に応じて適切な対応を取る必要があります。コーチングの内容やクライアントとの関係性によって様々なトラブルが想定されますが、以下のような対応が一般的な対応となります。
| 対応 | 詳細 |
|---|---|
| 事実確認 | 社員から事情を聞き、トラブルの内容や事実関係を正確に把握する |
| 関係各所への連絡 | クライアントや関係者への連絡を行い、状況を説明し必要に応じて謝罪する |
| 再発防止策の検討 | 同じようなトラブルが起きないように、就業規則の見直しや社員への研修などを実施する |
| 懲戒処分の検討 | トラブルの深刻度に応じて、社員に対して懲戒処分を検討する |
| 法的措置の検討 | 場合によっては、法的措置を取る必要が生じることもある |
コーチングの副業は、クライアントの人生や仕事に大きな影響を与える可能性があるため、トラブル発生のリスクも考慮しなければなりません。
企業は、就業規則で副業に関する規定を明確にする、社員への研修を実施するなど、事前に対策を講じておくことが重要といえるでしょう。
社員の「無形商材」の副業において気を付けるべきこと

副業の中でも、「無形商材」を扱うビジネスは特に注意が必要です。無形商材とは、コーチングをはじめ、情報商材・オンラインコンサル・デジタルコンテンツ・投資講座・スピリチュアル系セッションなど、形のない商品を提供するビジネスのことを指します。
これらは詐欺的手法や法的問題に発展するリスクが高いため、企業としても慎重な対応が求められます。無形商材を販売する副業では、以下のような問題が発生しやすいです。
-
誇大広告・詐欺的手法
-
知的財産権の侵害
-
クレーム対応が困難
-
違法ビジネスへの関与
無形商材の副業は、適切に運用されれば有益なものですが、一歩間違えると法的問題や社会的な批判の対象となる可能性があります。
企業としても、社員の副業リスクをしっかりと管理し、トラブルを未然に防ぐ体制を整えることが求められるでしょう。
【まとめ】コーチング副業のリスクを理解し適切な管理を
コーチングの副業は有益な一方で、トラブルを引き起こすリスクも伴います。
企業は就業規則を見直し、副業のルールを明確にすることで、適切な対応を取ることが重要です。
トラブル防止のために、法令遵守や適正な契約を意識し、責任ある副業活動を心がけるよう徹底しましょう。
運営