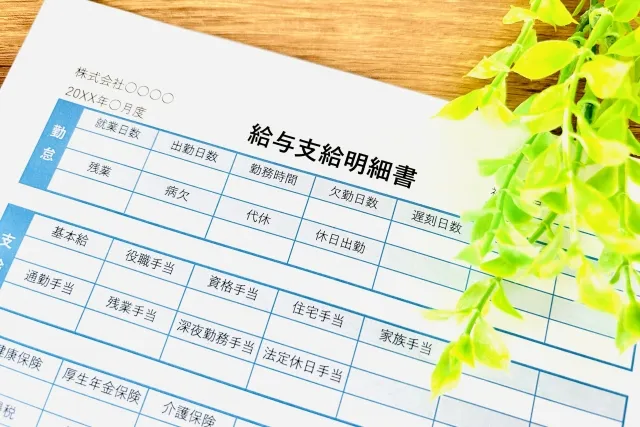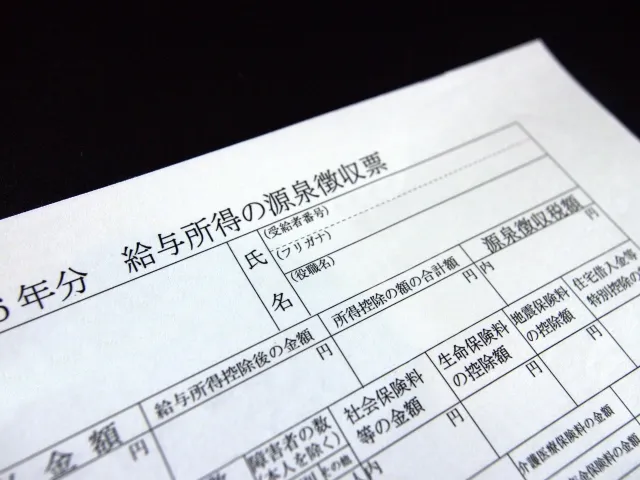社員が副業でECサイトを運営していたら?トラブル事例や対処方法をご紹介
社員が副業でECサイトを運営する場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。
本記事では、ECサイト運営にまつわるトラブル事例や、就業規則に基づいた対処法などを詳しく解説します。
トラブル発生時の適切な対応策を理解し、社員と会社双方にとって安全な職場環境づくりに役立ててください。
社員のECサイト運営は「副業」になる?

社員が本業のかたわらでECサイトを運営し、収入を得ている場合、それは一般的に「副業」とみなされます。
副業とは、本業以外で継続的に収入を得る活動を指し、たとえ趣味の延長として始めた場合でも、収益化を目的として運営している場合は副業と判断される可能性が高いです。
特に、ECサイト運営は、労力や時間を要するだけでなく、取り扱う商品やサービスの内容によっては、企業の利益と競合する可能性もあるため、企業としては慎重に対応することが求められます。
社員がECサイト運営の副業をしているときの対処法
ここからは、社員が副業をしている場合の対処法として、職業規則で副業を「禁止している場合」と「禁止していない場合」それぞれの対処方法を解説します。
就業規則で「副業」を禁止・制限している場合
就業規則で副業を禁止または制限しているからといって、社員のECサイト運営を即座に禁止・制限できるわけではありません。社員の勤務時間外の活動は、原則として社員の自由です。しかし、就業規則に則り、以下の場合に限り、例外的に禁止・制限が認められます。
厚生労働省のモデル就業規則では、以下の4つのケースにおいて、副業を禁止または制限できるとされています。
-
労務提供上の支障がある場合
-
企業秘密が漏えいする場合
-
会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
-
競業により会社の利益を害する場合
上記のいずれかに該当する場合、就業規則に基づき、ECサイトの内容を精査した上で、運営の禁止または制限を検討する必要があります。 社員の権利と会社の利益のバランスを考慮した、適切な対応が求められます。
就業規則で「副業」を禁止・制限していない場合
2018年1月、政府は「モデル就業規則」を改定し、副業・兼業を推進する動きを見せました。その結果、近年では副業を認める企業が増えており、就業規則で副業を禁止・制限していないケースも多くなっています。
社員がECサイト運営を届け出た際は、以下の点に注意し、必要に応じて就業規則の改定や個別の契約を検討しましょう。
-
労務提供への影響: ECサイト運営と本業の両立が可能か
-
企業秘密の管理: 企業秘密に関してルールの遵守を徹底しているか
-
コンプライアンス遵守: 景品表示法、特定商取引法、知的財産権などの法令違反がないか
-
競業避止: 自社事業と競合していないか
副業を認めている場合でも、会社の利益を損なう可能性がある場合は、活動内容の変更、または活動の停止を求めることができることを明確に伝える必要があります。
社員のECサイト運営によるトラブル例

ここでは、社員のハンドメイド副業で起きたトラブルを3つ紹介します。
-
サイバー攻撃によるシステム障害
-
個人情報の流出
-
クレジットカード情報を利用した不正注文
思わぬトラブルを避けるためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。
サイバー攻撃によるシステム障害
社員が副業で運営するECサイトがサイバー攻撃の標的となり、システム障害を引き起こすケースがあります。
2024年9月には、物流代行会社の関通がサイバー攻撃を受け、システム障害が発生しました。この攻撃により、個人情報の漏洩や配送遅延といった深刻な影響が生じ、多くの取引先や顧客に混乱をもたらしました。
企業側としては、社員がECサイトを運営する際に、セキュリティ対策の意識を徹底させることが求められます。具体的には、以下のような対策が効果的です。
-
強固なパスワードの設定
-
定期的なソフトウェアのアップデート
-
ファイアウォールの導入
-
不審なアクセスの監視
このような基本的なセキュリティ対策を徹底することで、サイバー攻撃を未然に防ぐ可能性があがります。また、万が一攻撃を受けてしまった場合に備え、被害発生時の対応フローをあらかじめ策定しておくことも重要です。
個人情報の流出
社員が運営するECサイトでも、個人情報の流出リスクは決して無視できません。ECサイトは顧客の名前、住所、電話番号、クレジットカード情報などの重要なデータを扱うため、適切なセキュリティ対策を講じなければ、サイバー攻撃の標的になり、情報漏洩の被害を招く可能性があります。
某ランドセルメーカーのECサイトでは、システムの脆弱性を突かれて第三者による不正アクセスが発生し、アプリが改ざんされた結果、16,396件の個人情報およびクレジットカード情報が流出した可能性があると報告されました。
これらの事件からもわかるように、ECサイトを運営する際には、サーバーのセキュリティ強化、不正アクセス防止策の実施、定期的なシステムアップデートなどが不可欠です。
クレジットカード情報を利用した不正注文
社員が運営するECサイトにおいて、クレジットカード情報を利用した不正注文は深刻なリスクの一つです。不正注文の中でも特に多いのが「なりすまし注文」で、これは第三者が他人のクレジットカード情報を盗み、それを使って商品を購入する行為を指します。
2024年には、某コーヒーチェーンのECサイトが改ざんされ、約93,000件の個人情報が流出し、そのうち53,000件がクレジットカード情報を含む可能性があると報告されました。
同様に、某大手家電メーカーのECサイトでも、5,836件の個人情報が流出し、そのうち4,257件がクレジットカード情報であったとされています。このケースでは、サイトが改ざんされ、注文確定時に入力された情報が第三者に送信されるプログラムが埋め込まれていたことが判明しました。
こうした事例からも分かるように、ECサイトを運営する社員は、不正注文の防止だけでなく、クレジットカード情報の保護にも細心の注意を払う必要があります。具体的な対策としては、以下の方法が効果的です。
-
セキュリティソフトの導入
-
SSL/TLSの適用(データの暗号化)
-
二要素認証の導入
-
不正アクセスの監視強化
上記の方法以外でも、3Dセキュアを活用し、カード所有者本人のみが決済できる仕組みを整えることも、不正注文を未然に防ぐ手段となります。
社員がECサイト運営の副業でトラブルに巻き込まれたら?
社員が副業でECサイトを運営する場合、顧客とのトラブル、サイバー攻撃、法律違反など、様々な問題に巻き込まれる可能性があります。
もし社員がECサイト運営の副業でトラブルに巻き込まれた場合、まずは状況を把握し、適切なアドバイスやサポートを提供することが重要です。
例えば、顧客とのトラブルであれば、対応方法を指導したり、社内規定に則った対応を促したりする必要があります。
また、法律に抵触する可能性がある場合は、専門家への相談を勧めるなど、適切な対応を支援をしましょう。
社員がECサイト運営の副業でトラブルを引き起こしていたら?
社員がECサイト運営の副業でトラブルを引き起こした場合、会社としての対応は迅速かつ適切である必要があります。
トラブルの内容によっては、会社の評判や信用に深刻な影響を与える可能性があるため、状況を把握し、事実関係を明確にすることが重要です。
もし社員が顧客とのトラブル、法令違反、情報漏洩などの問題を引き起こした場合、まずは社内規定に則り、厳正な対応を行う必要があります。具体的には、懲戒処分、損害賠償請求、業務改善命令などを検討する必要があるでしょう。
また、再発防止策を講じることも重要です。社員への研修や教育、就業規則の見直しなどを実施し、同様のトラブルの再発を防ぐよう徹底しましょう。
【まとめ】社員のECサイト副業、トラブル防止と適切な対応のために
社員のECサイト副業は、適切な管理と対応が必要です。副業によるトラブル発生を未然に防ぐために、就業規則の整備や社員教育を徹底しましょう。
万が一トラブルが発生した場合には、迅速かつ適切な対応を心がけ、社員と会社双方にとって健全な職場環境を維持することが重要です。
運営