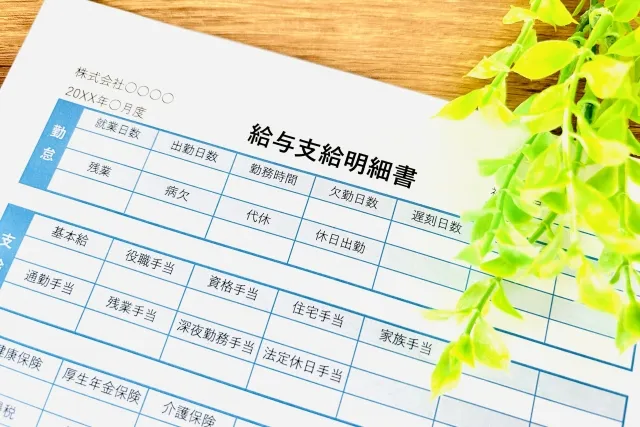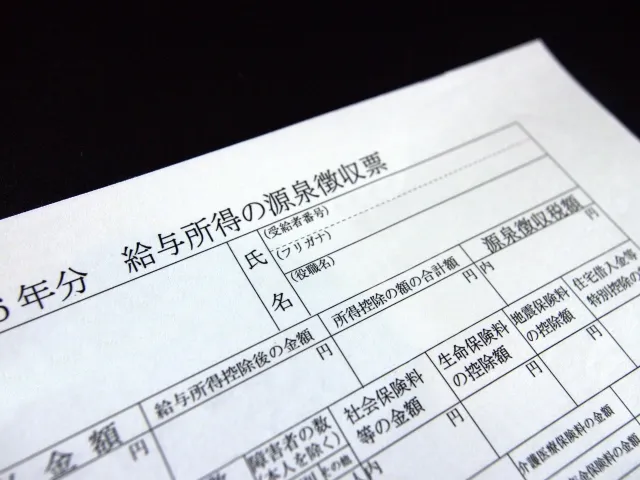社員が副業でYoutuberに!?実際にあったトラブルや対処方法をご紹介
社員が副業でYouTuberとして活動している場合、企業はどのような対応を取るべきでしょうか?
本記事では、社員のYouTube副業に関する法的リスクやトラブル事例、そして企業が取るべき対策について詳しく解説します。
企業と社員双方にとって安全で健全な活動となるよう、適切なルール作りを検討している人は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「Youtuber」は副業になる?

本業の傍ら、YouTubeに動画を投稿して収入を得る活動は副業になるのでしょうか?結論から言うと、YouTubeで収入を得る活動は副業とみなされます。
副業とは、本業以外に収入を得る活動全般を指します。会社員として働きながら、趣味の延長線上であっても、YouTubeで動画投稿を通じて収益化している場合は副業にあたります。
YouTubeで収益を得る方法はいくつかありますが、主に動画再生前や再生中に表示される広告収入が挙げられます。収益化するためには一定の条件を満たす必要がありますが、継続的に動画を制作・投稿し、実際に収入を得ている場合は副業と捉えられます。
法律で副業の定義が明確に定められているわけではありませんが、一般的には本業以外で継続的に収入を得るための活動が副業とされています。つまり、趣味の範囲を超えて、収益を目的としてYouTube活動を行っている場合は、副業とみなされる可能性が高いと言えるでしょう。そのため、企業は社員のYouTube活動について、就業規則に基づいた適切な対応が必要となるケースもあります。
社員がYoutuberの活動をしているときの対処法
ここからは、社員がYoutuberとして活動をしていることが発覚した場合の対処法として、職業規則で副業を禁止している場合と、禁止していない場合の対処方法について解説します。
就業規則で「副業」を禁止・制限している場合
就業規則で副業を禁止または制限しているからといって、社員のYouTuber活動を即座に禁止・制限できるわけではありません。社員の勤務時間外の活動は、原則として社員の自由です。しかし、就業規則に則り、以下の場合に限り、例外的に禁止・制限が認められます。
厚生労働省のモデル就業規則では、以下の4つのケースにおいて、副業を禁止または制限できるとされています。
-
労務提供上の支障がある場合
-
企業秘密が漏えいする場合
-
会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
-
競業により会社の利益を害する場合
上記のいずれかに該当する場合、就業規則に基づき、動画の内容を精査した上で、YouTuber活動の禁止または制限を検討する必要があります。 社員の権利と会社の利益のバランスを考慮した、適切な対応が求められます。
就業規則で「副業」を禁止・制限していない場合
近年、副業を認める企業が増えており、就業規則で副業を禁止・制限していないケースも多くなっています。
社員がYouTuberとして活動することを届け出た際は、以下の点に注意し、必要に応じて就業規則の改定や個別の契約を検討しましょう。
-
労務提供への影響:YouTuber活動と本業の両立が可能か
-
企業秘密の管理:企業秘密に関してルールの遵守を徹底させる
-
コンプライアンス遵守:著作権、肖像権、名誉毀損など、法令や社会倫理に反する動画投稿を固く禁じる
-
競業避止: 競合に関する活動の制限、自社事業との競合を避けるためのルールを明確に定める
副業を認めている場合でも、会社の利益を損なう可能性がある場合は、活動内容の変更、または活動の停止を求めることができることを明確に伝える必要があります。
社員のYoutube活動で起きたトラブル事例

ここでは、社員のYoutube活動で起きたトラブルを3つ紹介します。
-
名誉棄損をしてしまう
-
個人情報を流出してしまう
-
著作権を侵害してしまう
これらの問題は、YouTube活動を行う社員本人だけでなく、他の社員や企業全体にも影響を及ぼす可能性があります。思わぬリスクを回避するためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。
名誉棄損してしまう
YouTubeでの活動において、社員が動画内で他者や企業の名誉を傷つけるような発言をしてしまうと、名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損とは、事実かどうかに問わず、他人の社会的評価を低下させるような情報を不特定多数に伝達する行為を指します。
例えば他の社員のプライバシーを著しく侵害する内容や、犯罪者と決めつけるような内容は、たとえそれが真実でなくても、名誉毀損が成立する場合があるので注意が必要です。
企業にとっては、社員がYouTubeで自社や取引先、同僚の名誉を傷つけるような内容を発信することは、深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
特に、動画が広く拡散されると、企業の信用や評判が大きく損なわれる可能性があるため注意しましょう。
個人情報を流出してしまう
社員のYouTube活動においては、意図せず個人情報を流出させてしまうリスクがあります。例えば、近所の公園やレジャースポットなど、特定の場所を繰り返し撮影場所に使用すると、住所が特定される可能性が高まるでしょう。
また、動画内でうっかり自宅の様子や家族の情報を映し込んでしまうケースもあります。個人情報が特定され、暴露動画などで公開された場合、プライバシー侵害に該当する可能性があります。プライバシー侵害は民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求の対象となる可能性があるので注意が必要です(民法709条)。
個人情報流出は、被害者だけでなく、加害者である社員自身や会社にも大きな損害をもたらす可能性があるため、動画撮影や編集の際には、個人情報保護の観点から十分な注意を払うよう徹底させましょう。
著作権を侵害してしまう
社員のYouTube活動においては、著作権侵害に抵触するリスクも存在します。具体的には、以下の点が挙げられます。
-
音楽の無断使用
-
他者の動画の無断使用
-
映像・画像の無断使用
-
アニメや漫画の無断使用
著作権法第32条で定められた引用の要件を満たしている場合を除き、著作物を無断で使用することはできません。著作権侵害は法的責任を問われる可能性があるため、動画作成においては著作権について十分に注意する必要があります。
トラブルを未然に防ぐために必要なこと
社員のYouTube活動によるトラブルは、企業にとって大きな損害をもたらす可能性があります。特に、一度公開された情報は瞬時に拡散してしまうため、事後対応では大きなダメージを受ける可能性があります。そのため、トラブルを未然に防ぐための対策を講じることが重要です。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| SNSに関する社員研修の実施 | 従業員向けに、SNS利用に関するリスクや注意点、法令遵守、企業倫理、情報管理などをテーマにした研修を実施 |
| ソーシャルメディアポリシーの策定 | 社員のSNS利用に関するガイドラインを策定し周知徹底する |
| 就業規則の改定 | ーシャルメディアポリシーに違反した場合の罰則規定を就業規則に盛り込みポリシーの実効性を高める |
ソーシャルメディアポリシーには、以下のような項目を入れると効果的です。
-
勤務時間中の動画撮影・投稿の禁止
-
労務提供への支障が生じない範囲での活動
-
企業秘密情報の漏洩防止
-
炎上や風評被害につながる行為の禁止
-
競合他社の商品・サービスに関する言及の制限
-
著作権・肖像権等の権利侵害の禁止
-
会社の承認を得ない上での、会社との関係性を明示した活動の禁止
これらの対策を事前に講じることで、社員の不用意な行動によるトラブルを未然に防ぎ、企業の評判や利益を守ることができるでしょう。
【まとめ】社員のYouTube副業、適切な対応でリスク管理を
社員のYouTube副業は、適切な対応を怠ると企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。就業規則の整備やソーシャルメディアポリシーの策定、社員教育などを通じて、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
この記事を参考に、企業と社員双方にとって安全で健全なYouTube活動のルール作りを検討してみてください。
運営