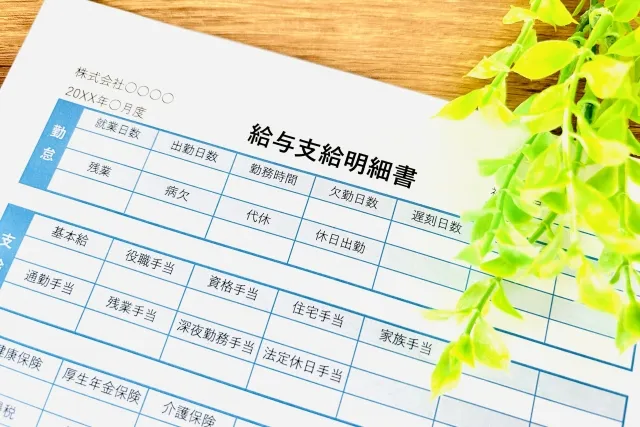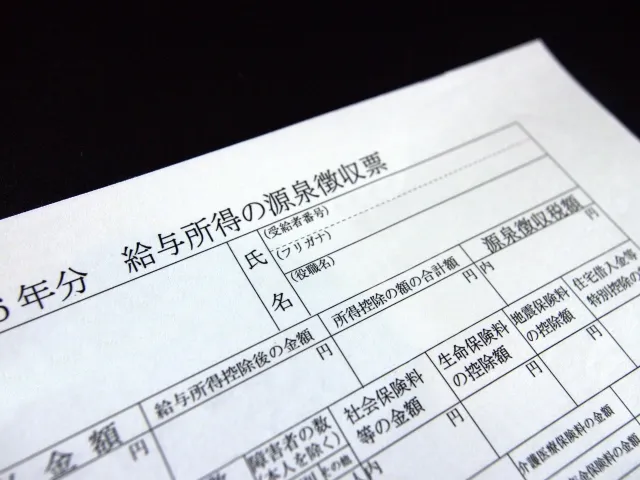企業が副業を禁止とするのは違法?公務員のケースや副業導入のメリットもご紹介
副業を禁止することは違法なのでしょうか?公務員と民間企業では、副業に対する規制が異なります。
この記事では、副業に関する法律や、企業が副業を制限する理由や副業導入のメリット、そして政府の副業推進の姿勢について解説します。
副業を禁止することはできない

法律上、企業は会社員に一律で副業を禁止することはできません。
憲法第22条1項で職業選択の自由が保障されているため、どんな仕事を掛け持ちするかは基本的に本人の自由です。
企業は就業規則等で独自のルールを設けることができ、副業を禁止または許可制にしている企業も存在しますが、企業による副業の禁止・制限は必ずしも認められるわけではありません。
裁判例では、副業を禁止・制限することは基本的に認められず、以下の様な弊害が生じる場合に限り、企業が副業を禁止・制限することを許容する傾向にあります。
-
労務提供上の支障がある場合
-
業務上の秘密が漏洩する場合
-
競業により自社の利益が害される場合
-
自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
公務員の場合法律で一定の副業が制限される

法律上、企業は従業員の副業を禁止することはできませんが、「国民全体の奉仕者」としての公務員は、以下の法律で明確に副業が禁止されています。副業を考えている人や既に副業をしている公務員の方は注意が必要です。
-
国家公務員法第103条
-
国家公務員法第104条
-
地方公務員法第38条1項
国家公務員法第103条
国家公務員法第103条では、報酬の有無に関わらず、営利企業における副業を制限しています。
以下のような副業をする場合、人事院の承認が必要です。
-
営利企業の役員、顧問、評議員等の兼業
-
営利企業の自営
つまり、公務員が営利企業の社員や役員、顧問や評議員として副業をすることは法律により禁止されています。
また「自営」とは、一定規模以上の不動産・駐車場などの賃貸、太陽光発電による売電、農業なども該当すると解釈されています。
参照:国家公務員法
国家公務員法第104条
国家公務員法第104条は、営利を目的とする企業の役員等兼業や自営業以外で、報酬を得る副業を制限するものです。
営利企業以外で、「労働の対価として報酬を得る」かつ「事業又は事務に継続的又は定期的に従事する」場合には、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要となります。
参照:国家公務員法
地方公務員法第38条1項
地方公務員も、国家公務員と同様に副業が制限されています。
地方公務員は原則として、任命権者の許可がない限り、以下の副業は禁止されています。
-
営利企業の役員等の兼業
-
営利企業の自営
-
報酬を得て事業または事務に従事すること
ただし、非常勤職員(※)はこの限りではありません。
※短時間勤務の職を占める職員および地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く
参照:地方公務員法
公務員が副業を制限される理由
公務員の一定の副業が法律で制限されているのは、公務員が国民全体の奉仕者であることが求められているためです。
副業によって特定の業種に利益を与えていると捉えられかねる行為は望ましくないとされています。
公務員の職務に専念し、国民への奉仕に集中するためにも副業は制限されているのです。
企業が副業を制限している理由
公務員はその性質上「副業は禁止」と法律で定められていますが、一般企業が従業員の副業を制限する理由は、主に企業の利益損失を防止することが目的です。具体的には、以下のようなリスクが挙げられます。
-
優秀な従業員が流出する恐れ
-
過重労働を助長する恐れ
-
利益相反につながる恐れ
-
企業ブランド価値を毀損する恐れ
優秀な従業員が流出する恐れ
副業が成功した場合、従業員が本業を辞めて副業に専念する可能性があります。
特に優秀な人材ほど副業で成功する可能性が高いため、企業にとっては大きな損失となります。
副業によって本業で得られる以上の収入や満足感を得られるようになった場合、流出リスクはさらに高まるでしょう。
また、副業に時間を割くことで、本業へのモチベーションが低下し、パフォーマンスが落ちる可能性も懸念されます。
特に、本業で思うような昇進が無かったり、仕事内容に不満を抱えている場合、副業に傾倒していく傾向が強まります。
結果として、本業でのパフォーマンス低下を招き、企業にとっては損失につながります。
過重労働を助長する恐れ
副業を行うことで、従業員の労働時間が増え、過重労働につながることも、企業が副業を制限する理由の一つです。
本業に加えて別の仕事を行う副業は、従業員に過度の負担を強いる可能性があり、健康被害を引き起こす懸念があります。
企業には従業員の健康と安全を守る責任があるため、過重労働を抑制し、従業員の健康リスクを最小限に抑える必要があることから副業を制限するのです。
利益相反につながる恐れ
従業員の副業が本業と競合する場合、利益相反が発生するリスクがあります。
例えば、本業で扱う商品と類似した商品を副業で販売する場合、顧客や取引先が重複し、企業の利益が損なわれる可能性があります。
このような利益相反のリスクを回避するためには、社内規程に以下のような項目を明確に設けることが効果的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 副業の申請制度 | 副業先が競合に該当しないか、副業先での勤務時間や役職などを事前に申請する仕組みを導入 |
| 副業先での禁止事項 | 競合企業への従事や企業秘密の漏洩につながる行為を明文化 |
| 罰則制度 | 規程違反が発生した場合の具体的な罰則を設け、違反行為の抑止力を高める |
| 機密保持契約の締結 | 本業で得た情報が副業先で不正に利用されないよう、従業員と機密保持契約を結ぶ |
このような項目を社内規程に設けたうえで、規定を運用面で定着させるために、定期的なモニタリングを実施することが重要です。従業員との定期的なコミュニケーションを通じて規定の内容を浸透させることで、利益相反の発生を未然に防ぐ環境を構築できます。
企業ブランド価値を毀損する恐れ
従業員の副業内容によっては、企業のブランドイメージに悪影響を与える可能性があります。
例えば、違法行為に関わる副業や、社会的に問題視されている活動に従事している場合、企業の評判が低下し、ブランド価値を毀損する恐れがあります。
企業は自社のブランドイメージを守るため、副業内容を制限する場合があります。
副業・兼業の雇用形態で従業員を受け入れる目的

一方で企業が副業・兼業として他社の従業員を受け入れるのは、以下のような目的が考えられます。
-
人材確保
-
自社で活用できる他社の知識・スキルの習得
-
生産性向上
副業・兼業という柔軟な雇用形態は、従来の正社員雇用では難しかった多様な人材の採用を可能にします。
また、他社で培われた専門知識や技術を取り入れることで、自社に新たな価値をもたらす効果が期待されます。
さらに、必要に応じて即戦力を投入できるため、プロジェクトの効率的な遂行や業務の迅速な改善に繋がります。
政府は副業・兼業を推進の姿勢
近年、政府は働き方改革の一環として、副業・兼業を推進する姿勢を明確にしています。
厚生労働省は2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、副業・兼業を原則として認める方向性で示されており、企業に対し、副業・兼業を促進するための環境整備を推奨しています。
さらに、2027年度には希望者全員が原則として副業を行うことができる社会を構築することを計画しています。
【まとめ】副業の適切な管理で企業と従業員の利益を守る
副業の禁止や制限には、公務員や企業それぞれの事情がある一方で、政府は副業を推進する姿勢を明確にしています。
この記事の内容を参考に、職場環境に適した副業管理の方針を検討してみてください。
労働者の多様な働き方を尊重しつつ、企業としての利益と秩序を守る仕組みを構築することが重要です。
運営